成長する人のマインドセット
 |
BCGの特訓――成長し続ける人材を生む徒弟制 木村亮示 木山聡 日本経済新聞出版社 2015-11-20 |
「人材育成」はいつの時代でも企業の課題の一つです。
「人が足りない」という言葉は、「頭数が足りない」ではなく、「優秀な人がいない」という意味になります。
日本においては労働人口のピラミッドが歪になっていく中、今後この課題は
今以上に問題になっていくでしょう。
本書では、育成する側、される側双方の観点から、以下の内容が記載されています。
・育成する側:できる人を効果的に育てる方法
・育成される側:「成長する人」になるためのマインドセット
二人の著者はボストンコンサルティング(BCG)で人材育成に関わる方々であり、
BCGで実際に行われている「多様な人材を超高速で戦力化する技術」が紹介されています。
本エントリーでは「育成される側」のポイントについて絞って紹介します。
■スキルマニアの罠
自分に不足していると感じているスキルを次々に学んでいくが、
それがなかなか成果に結び付かないというタイプの方はある「罠」にハマっています。
それはチェックボックスメンタリティというもので、不足している部分を次々と埋める事で
「スキルを身につける事=成長」
と勘違いしてしまう事です。
本書では2つのタイプのスキルマニアがいると述べています
・コレクション型:前述したタイプ
・突き詰め型:ある特定のスキルを突き詰める事で周りからは重宝されるが、
「便利屋」の要に使われてしまう
これらスキルマニアから脱出するためには「何を身につけるか」から
「どう使うか」という状況判断力が必要になります
■成長する人の3つのマインドセット
スキル偏重の考え方から「成長する人」になるためのマインドセットを
本書では3つあると紹介されています。
1. 他者への貢献に対する強い想い
非常に逆説的ではあるが、「成長したい」というのが主たる動機で
仕事をしている人は、十分な成長が見られない傾向がある。
(中略)
しかし、本来、成長は”手段”にすぎない。
(中略)
「クライアントの役に立てるようになるために成長したい」という気持ちが、
一番強い成長の原動力になるのだ。2. 何度もチャレンジを継続できる折れない心
できるかできないか不明な状況でも足を止めず、あきらめずにやってみないと、
成長はできないのだ。3. できない事実を受け入れる素直さ
長期的に成長して成功しているコンサルタントには、失敗したときや
うまくいかないとき、まず「自分に原因があるのではないか」と考え、
客観的に振返る素直さや謙虚さが備わっている。そこから改善点を見つけて、
建設的により良い解ややり方を追求していく事ができる。
引用が長くなりましたが、個人的な戒めも含めて上記内容は非常に重要なことです。
資料作成やプレゼンのスキルを追い求めることが目的化してしまうと、
スキル偏重に陥ってしまいます。
■学びの面積を増やす
成長のスピードを上げていくためには、時間の使い方が大事です。
「学びの面積を増やす」とは、質を上げて、量を増やすことです。
本書では著者らの経験から以下の方法が上げられています。
<量を増やす>
・オンの時間を増やす
情報に対して常に「自分ごと」として捉える。学びのアンテナを
オンにしておくことで、他人の経験までも自分のものにすることができる
<質を上げる>
・目を肥やす
自分だったらどうするか、という見方をする
・行動を分解する
「振返り➡分析➡整理➡応用」というサイクルをまわす。
・実践する、変化する
PDCAを素早くまわす
■編集後記
本エントリーでは「育成される側」について紹介しましたが、
「育成する側」のポイントについても、具体的に記載されていますので、
気になる方は本書をご覧ください。
また、「無意識の思考のクセ」という箇所で記載されていた出身別のクセは
個人的にヒットでした。
SE・プログラマー出身者の思考パターンは「完璧主義」
SEやプログラマー(特に大規模なシステム構築に携わってきたタイプ)には、
ロジカルではあるものの、完璧主義で、細部に至るまで整合性を担保しようという
傾向が強い
かなり当たってます。

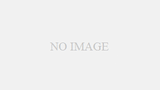
コメント